ご来場をいただきまして、誠にありがとうございました。
下記より、当日の模様を各所員ごとに抜粋し、お伝えします。
2017年度 多摩美術大学 芸術人類学研究所+芸術学科21世紀文化論 共催
第5回「土地と力」シンポジウム『イメージの発生』
会場:多摩美術大学八王子キャンパス・レクチャーホールB
日時:2017年11月18日(土) 開演13:15(開場12:45) 終演16:10
入場無料・事前予約なし
芸術のもつさまざまな可能性を人類学的に探究することを目的として創設された芸術人類学研究所は、新たなディケイド(10年期)にむけて最初の一歩を踏み出す。研究所開所11年を迎えて、昨年の「聖なる場所のネットワーク」に続き、鶴岡真弓所長以下、平出隆、港千尋、椹木野衣、安藤礼二の全所員が参加し、芸術表現の根源、「イメージの発生」について、それぞれの専門分野から、最新の知見を持ち寄り、共同討議を行う。ケルトに伝承された循環生命論、詩をつらぬく物質的想像力、自然と人工の差異が消滅する多孔空間、「太陽の塔」と生命の樹、縄文・アイヌ・洞窟壁画、等々の主題から、新時代を切り拓く芸術研究のマニフェストが立ち上がる。
|
冒頭の所長挨拶は、芸術のゲネシス(創生)に光が当てられた。人類/人間が、主体的に感動をもって、何かを生み出すことに力を注ぎ、この地上に初めて、えもいわれぬ美が誕生した。その瞬間が芸術のゲネシス、発生であった。 動物でも機械でもなく、その両者の中間に位置する人間が、その存在証明のようにして持つことができたのがイメージ的な思考、すわなち芸術である。 本シンポジウムでは、イメージの発生にして芸術の発生―言語と形象を、お互いに異なり合いながらも交響し合う、さまざまな視点から掘り下げた。所員5名が芸術表現の根源、「イメージの発生」をテーマに、それぞれの専門分野から新たな知見を発表した。
|
 |
||
 |
安藤所員の報告「アイヌ・縄文・洞窟壁画―アンドレ・ルロワ=グーランと造形的思考の起源」は、はじめてフランスの洞窟壁画を評価した社会人類学者ルロワ=グーランと、彼のアイヌの村での調査取り上げた。過去と未来の出来事が網羅された「野生の書物」としての洞窟の重要性と、その今日性を指摘した。 | ||
| 港所員の報告「洞窟から―多孔性モデルとイメージの発生」では、穴だらけの社会を多孔性、穴をふさぐ近代的社会を緩衝性として捉えた。ショーヴェ洞窟、ラスコー洞窟、パルマ大聖堂の礼拝堂の紹介を通じて、すでに無くなったように見える多孔性の世界が、いまだ現代に連続し、継承されているのではないか、と問うた。 |  |
||
 |
椹木所員の報告「空洞の洞、地底の顔」は、2018年3月に一般公開が控えている岡本太郎の《太陽の塔》制作構想や、そこに通底する思想の検証を行った。岡本が残したメモの一文「ひろがることによって逆に根にかえっていく」を皮切りに、《太陽の塔》地下空間の根源的な抽象形態について掘り下げた。高度経済成長期に制作された《太陽の塔》には、反近代的意図が込められていたことを示唆した。 | ||
| 平出所員の報告「物質的想像力と《インク》による書物論」では、フランスの科学哲学者ガストン・バシュラールの概念「物質的想像力」を取り上げた。バシュラールの想像力論の要は、固定的なものの絶えざる否定にある。今回はインクと紙の物質性を例に、書物と想像力との関係を掘り下げた。報告の最後には、詩学と科学の出会う場として、平出所員の書物論《空中の本へ》を提示した。 |  |
||
 |
鶴岡所長の報告「ケルト・アイルランドの『巌・島・海』の異界と『生命循環』論」は、「ゲネシス(創生)」の読み解きからはじまり、人間を主人公にした現代の「人間の世界」を批判し、「生きとし生けるもの」の一員としての人間認識の必要性を訴えた。その後、イサム・ノグチの《エナジー・ヴォイド》、アイルランドのスケリグ島の巌やモハーの崖を例に取り、虚(ヴォイド)空間および虚無的深淵の哲学的重要性を指摘した。
上記の例にあげたような深淵は、生命循環の場、生と死と再生の場所でもある。「イメージの発生」とは一回性の中にあるものではない。それはむしろ「循環に踏み出す最初の一歩」であった。 |
||
| 今回のシンポジウムでは、上記のような各所員の報告によって「イメージの発生」というテーマを、芸術人類学的に深化させることができた。
それぞれの内容を継承するように報告が進み、2回の討議では、各報告が循環するように、言葉どおり芸術のゲネシス(創生)と再生が浮かび上がった。 右は所員5名の集合写真。 |
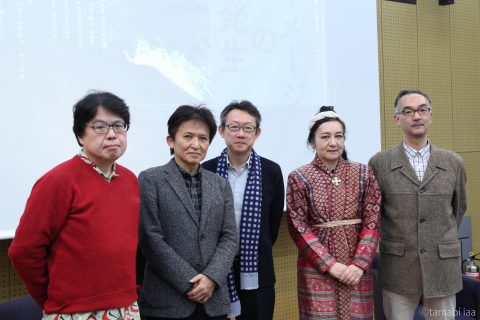 |
||
詳細は、幣研究所発行の刊行物『Art Anthropology」13号(2018年4月以降)に掲載しております。こちらのホームページ(トップインフォメーション)でもお知らせいたしますので、よろしければご覧ください。