
川瀬智之(かわせ・ともゆき)
東京藝術大学准教授。美学研究者。
1971年神奈川県に生まれる。1994年多摩美術大学美術学部芸術学科を卒業後、東京大学大学院人文社会系研究科に進学し、2008年に博士号を取得。多摩美術大学では、2007年から非常勤講師として務めている。専門は美学。著書に『メルロ=ポンティの美学芸術と同時性』(2019年)。
学生時代に「美学」に目覚める
本学科十期生として当時の「スタディ系」コースで現代美術を学ぶ中で、「美学」に目覚めた。鑑賞者の感動のありようは、時代によって大きく変化し続ける。コロナ禍の下では、美術作品を見る側も作る側も意識が変わっていくと推測する。
二〇二〇年は新型コロナウイルスの影響が著しく大学の講義などの多くがオンラインでの実施になる中で、この取材もリモートで行われた。そしてリモートであるにも関わらず、しっかりとスーツを着ている川瀬智之さんの姿からは、何ごとにも真摯に取り組む実直さが伝わってきた。
川瀬さんは、一九八一年に創設された多摩美術大学芸術学科の十期生。現在は東京藝術大学芸術学科で准教授を務めるかたわら、本学でも非常勤講師として教鞭を執っている。
二十世紀の芸術に関する哲学的思想の研究を専門にする現在の道に進むことになったきっかけは、大学二年生の時に受講した黒川弘毅先生の授業だった。選択必修の実技の授業の中で黒川先生が言った言葉、〞芸術は〈存在〉と存在者を媒介する天使だ〞という言葉に衝撃を受け、芸術においても哲学が存在し、重要な役割を担っているということを学ぶ。尚、今でも川瀬さんは美学の授業のはじめにいつもこの言葉を紹介するそうだ。美術を深く理解するためには、芸術や美についての哲学、すなわち「美学」を知ることが重要であると気づいたのだ。本学科での学生生活は、今の川瀬さんの根幹を形成する大切な時期となった。
初めは、鑑賞者が絵を見て感動する時に心の中で何が起こっているのかということに関心があったが、現在は「芸術家がどういう風に世界を捉えているのか」ということを考えるようになり、芸術分野における哲学を研究している。川瀬さんは小さい頃から二十世紀イタリアの画家ジョルジョ・デ・キリコがお気に入りだった。シュルレアリスム(超現実主義)につながる、極めて不思議な空気感を持つ作品を描いた画家だ。最近はインド出身のアニッシュ・カプーアや米国出身のビル・ヴィオラのような、「芸術と哲学と宗教を重ねて芸術作品を作り、世界を超越した何かを芸術でつかもうとしてるアーティストに興味を惹かれている」と言う。そして、小さい頃から画集や絵を見ることが好きだった川瀬さんは、今も昔も共通して、現実を超えた世界の作風をもつアーティストに深い関心を持っているという。
「美術史では、誰が何のために作品を作ったのかということなどに研究テーマがフォーカスされますが、美学は違う。そもそも、〝芸術とは何か〞〝なぜ自分は感動するのか〞ということを疑問に思う人のための学問です」
言い換えれば、美学は鑑賞者にフォーカスする学問ということになる。鑑賞者の感動のありようは、時代によって大きく変化し続ける。古典絵画などの作品が生まれた時点と現在とでは、作品そのものは変わっていなくても鑑賞者の受け止め方は異なっている。美学はそんな背景のうえに成り立っているのだ。
今、世界の人々は歴史的な感染症になるであろう新型コロナウイルスと対峙している。コロナ以前と以降でも、美の価値観は変化しうる。川瀬さんは、「インターネット時代になった現代では、絵の具の物質感や大きさの感覚が鑑賞体験からは抜け落ちる」という変化があることに触れ、そのスピードがコロナ禍による外出自粛等のために急速に増していると指摘。その結果、見る側だけでなく作る側も画像として見られることを意識した作品を制作するようになっていくのではないかと推測する。鑑賞者の行動や意識の変化が制作者の行動にも影響を及ぼすというわけだ。
人は何のために生きているのか。一つの答えとして「自身の持つ知識を後の代に伝える」ということがありうるのではないだろうか。人類はそうやってさまざまな哲学や技術を展開・継承してきたのだ。教員はいわば、そうした人間の奥底にある意識に根ざした仕事をする役回りともいえる。川瀬さんは「芸術についての考え方はそれぞれの時代の中にある」との考え方のうえに立って、授業では「いろいろな考え方を提示し、その中から学生一人ひとりがこれだと感じたものを選べるようにする」ことを理念としているそうだ。特に美大には、それぞれの考え方に強いこだわりを持った学生が集まっている。その中でも芸術学科はとりわけ多様といえる。川瀬さんの言葉は、芸術学科の特質をも明らかにしている。
取材・文・レイアウト=赤荻李香、向リサ
※本記事は『R』(2021)からの転載です。
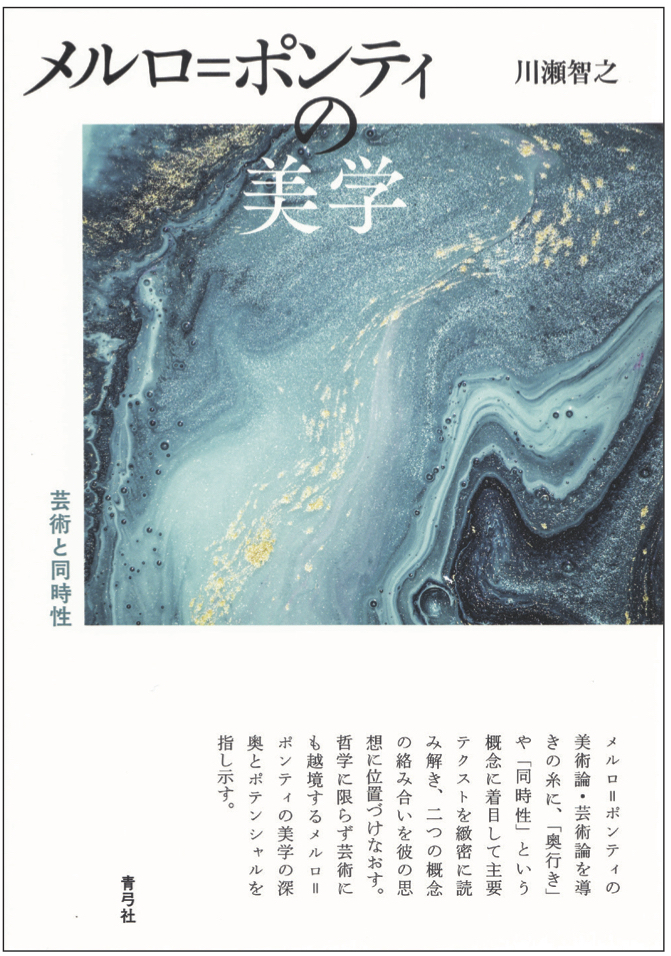 川瀬智之『メルロ=ポンティの美学 芸術と同時性』(青弓社、2019年)(*)
川瀬智之『メルロ=ポンティの美学 芸術と同時性』(青弓社、2019年)(*)