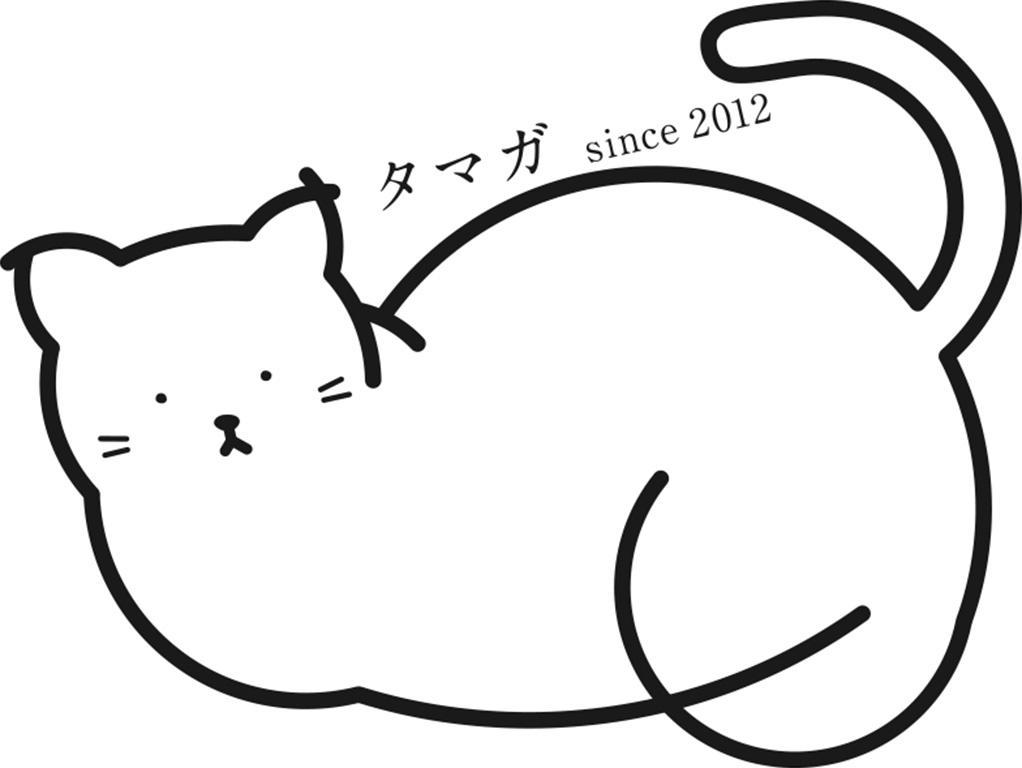大型で強い台風18号が、東京23区付近を北東へ抜けようとしていた10月6日午前10時。彫刻家の安田侃による、まゆのような形をした大理石のオブジェ『意心帰』の周りでは、何やら緊張した面持ちで人々が集まっていた。ここは、東京ミッドタウンのプラザ地下1階。一般の人々が多く行き交う中で行われていたのは、「Tokyo Midtown Award」アートコンペの 最終審査だった。
1枚の食パンに飛びつくように群がる人々を描いた屏風状のパネルが立っていたり、ミニチュアの石庭のようにしつらえたアイスクリーム販売用のフリーザーの中にペットボトルやプラカップらしき何かが配置されていたり、雑草が生えたようなコンクリートのブロック塀がいきなり置かれていたり…。立体作品が多いのはこのコンペの特徴なのだろう。審査員の面々は作品の前で作家のプレゼンを聞く。作品のコンセプトだけではなく、「なぜその素材を使ったのか」「なぜその展示方法を取ったのか」といった様々な問いを作家たちに投げかけ、答えをもらう。この場での審査は1時間ほどで終わった。


今年で7回目を迎える「Tokyo Midtown Award」は、次世代を担うアーティストとデザイナーの発掘と応援を目的に2008年に始まった。審査の流れはこうだ。まず、書類による一次審査で12人に絞られる。二次審査は、模型の制作とプレゼンテーション。残ったファイナリスト6人に、それぞれ制作費として100万円が補助される。東京ミッドタウンのオープンスペースを会場にして、完成作品の審査が行われる。

賞金のほかに制作費の補助が出るのは、若き作家たちが存分に腕を振るう大きな助けになるはずだ。主催の東京ミッドタウンマネジメントは、三井不動産の系列会社。企業による現代的なパトロネージュのあり方を問う試みと言える。
アート部門の審査員はフリーランス・キュレーターの児島やよいさん、東京ミッドタウン・アートワークディレクターの清水敏男さん、彫刻家の土屋公雄さん、アーティストの中山ダイスケさん、メディア・アーティストの八谷和彦さんの5人。作品の前で作家は5分という限られた時間の中で自らの作品をアピールする。 審査に際して作家本人の主張が加味されるのは、現代アートならではのことだろう。
「Tokyo Midtown Award」が他のアートコンペと違うのは、美術館のような閉じた空間ではなく、パブリックスペースである通路に作品が展示されることだろう。いわば、東京ミッドタウンという”街”にアートを展示するわけだ。
「このアワードでは、パブリックな場所で作品がどう主張できるかが重要」と語るのは、第1回目からこのアワードに関わる審査員の一人、清水敏男さんだ。現代は、アートは美術館で見るというのが半ば当たり前になっているが、美術館が存在する前から生活や日常の場にアートはあった。ところが、近代以降美術館が増えると、アートはむしろ日常の場からは減ってしまった。「このアワードには、日常の中にアートを取り戻そうという思いもある」と清水さんは言う。
さて、今年の「Tokyo Midtown Award」ではどの作品がグランプリに選ばれただろうか。(後編へ)


取材・文=韓松鈴
撮影=ミヤザワカナ
「タマガ」とは=多摩美術大学芸術学科フィールドワーク設計ゼミが発行しているWebzine(ウェブマガジン)です。芸術関連のニュース、展覧会評、書評、美術館探訪記、美術家のインタビューなどアートにかかわる様々な記事を掲載します。猫のシンボルマークは、本学グラフィックデザイン学科の椿美沙さんが制作したものです。