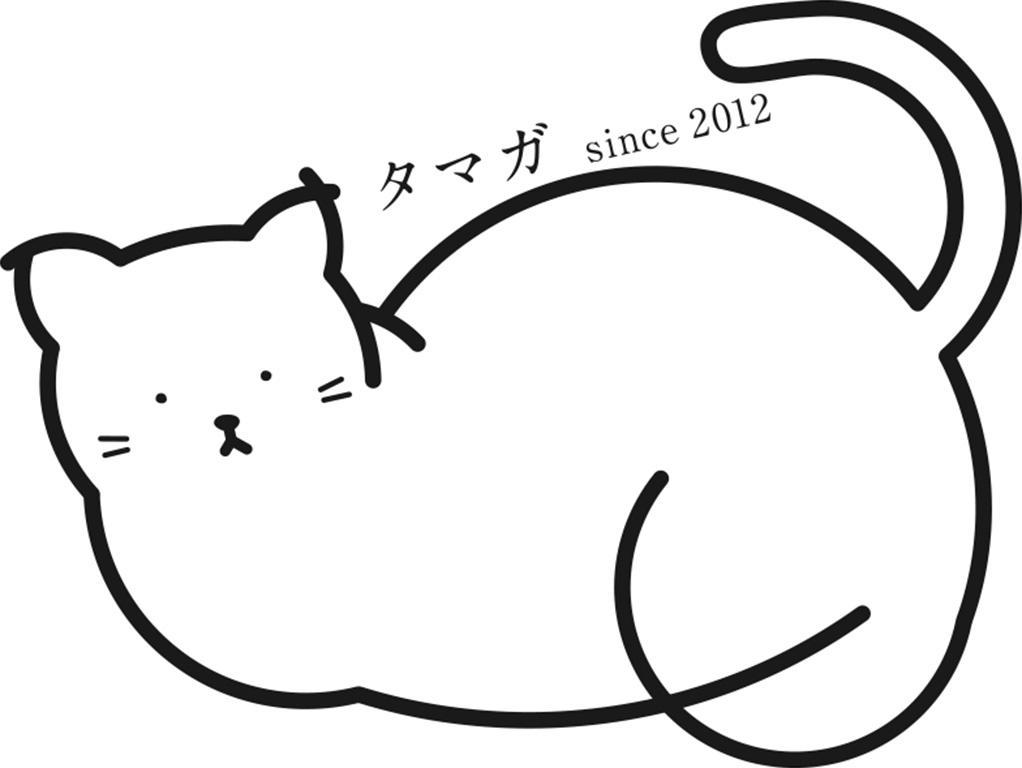東京・上野の国立西洋美術館で「シャセリオー展 19世紀フランス・ロマン主義の異才」が開催されている。19世紀フランスの画家シャセリオーは、かのアングルのもとで学び画家として順調な道を歩み始めながらも、やがて師とは決別。さらにはアルジェリアへの旅が新たな展開をもたらした。

テオドール・シャセリオー《自画像》(1835年、 ルーヴル美術館所蔵) Photo©RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi / distributed by AMF)
「タマガ」とは/本学科フィールドワーク設計ゼミが発行しているウェブマガジンです。芸術関連のニュース、展覧会評、書評、美術館探訪記、美術家のインタビューなどアートにかかわる様々な記事を掲載します。
東京・上野の国立西洋美術館で開かれている「シャセリオー展 19世紀フランス・ロマン主義の異才」に足を運んだ。不勉強ながら、テオドール・シャセリオー(1819〜56年)は初めて聞く名前だった。19世紀フランスといえばミレーなどのバルビゾン派や印象派の時代だが、実際に同館でシャセリオーの作品を見ると、どちらかといえば写実的な表現を得意としている。モネやルノワールとはまったく違った画風から、一体どんな画家だったのだろうと逆に興味が湧いた。
展覧会を見てまず分かったのは、シャセリオーが独特のポーズの裸婦を描いた《グランド・オダリスク》や《泉》などの作品で知られるドミニク・アングルの弟子だったことだ。しかし、弟子はまた独自の道を歩んだことが分かった。

テオドール・シャセリオー《自画像》(1835年、 ルーヴル美術館所蔵) Photo©RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi / distributed by AMF)
展示室に入って最初に目にしたのは《自画像》だった。灰色と緑色が混ざり合った風景に、黒い厚手のコートを着て、顎のあたりまで垂らしたこげ茶の髪をカールした画家が左手をコートの中に差し込み、赤いクロスがかかった台の上にある本に手を伸ばしながら、こちらを見ている。制作年は1835年、10代なかばの作品だ。同展のカタログによると、シャセリオーはどうも美男子とは言いがたい人物だったようだ。後に恋人となる女優アリス・オジーからは、「醜い小男」と呼ばれていたという。しかし自画像はなかなか端正でスマートだ。この頃はドミニク・アングルに就いており、将来を前向きに見る自分を描こうとしたのかもしれない。実際、翌年には当時のフランスの画家のエリートコースだったサロン(官展)に入賞する。
しかし、1840年を境に師であるアングルと決別する。師を追うばかりが能ではないのは確かだ。そして歩み始めたのが、ロマン主義への道である。神話を題材にこの時期描いた《アポロンとダフネ》が見せる官能性の高い表現を目の当たりにして、まるで舞台の一場面に自分が立ち会ったかのように作品の世界に引きずり込まれた。
旅は誰にとってもいい経験になる。その後シャセリオーに大きな変化もたらしたのは、1846年のアルジェリア旅行だった。アルジェリアは北アフリカにあるが、長らくオスマン帝国の支配下にあって東方の文化が流入する。シャセリオーが生きた時代には、フランスが植民地にした。

テオドール・シャセリオー《コンスタンティーヌのユダヤ人街の情景》(1851年、 メトロポリタン美術館蔵) Image copyright©The Metropolitan Museum of Art. Image source: Art Resource, NY)

テオドール・シャセリオー《気絶したマゼッパを見つけるコサックの娘》(1851年、 ルーヴル美術館蔵、ストラスブール美術館寄託) Photo©Musées de Strasbourg, Mathieu Bertola)
「実際に体験した、生き生きとして、現実的なオリエントを表現するのか? それとも夢想され、再構成され、理想化されたオリエントを連想させるのか?」 帰国したシャセリオーは、自分の中で2つの意見を戦わせたという。たとえば《コンスタンティーヌのユダヤ人街の情景》と《雌馬を見せるアラブ人の商人》では、赤ん坊を寝かしつける家族の姿や馬を売る商人を取り巻く人々という現実の風景を描いた。しかし《気絶したマゼッパを見つけるコサックの娘》はどうだろう。死んで虚ろな目をした馬の上に折り重なるように倒れたウクライナの英雄マゼッパの前に立つのは、コサックの少女である。この構図は、絶望の中にも美の世界に昇ることが可能な道があることを思わせる。その重要な役割を果たしているのが、少女が着た民族衣装である。
《泉のほとりで眠るニンフ》のモデルは、1849年に出会い画家の人生を翻弄した女優のアリス・オジーだった。鬱蒼と茂った森の中で体を横たえたニンフの、何と官能的なことか。彼女が脱ぎ捨てたらしきバラ色のドレスや金の首飾りは、この裸婦が実は神話のニンフではなく、19世紀の同時代の女性であることも明かしているという。1856年に描いた《東方三博士の礼拝》は、登場人物の服装が中東の民族衣装に似ている。旅で見たオリエントの現実が、聖書という物語の世界の中で生きている。シャセリオーは、旅を経て、物語に現実味を帯びさせた画家と言えるのではないだろうか。
取材・文・レイアウト=椋田大揮

テオドール・シャセリオー《泉のほとりで眠るニンフ》(1850年、CNAP、アヴェニョン、カルヴォ美術館寄託) ©Domaine public / Cnap /photo: Musée Calvet, Avignon, France)

テオドール・シャセリオー《雌馬を見せるアラブ人の商人》(1853年、 ルーヴル美術館蔵、リール美術館寄託) Photo©RMN-Grand Palais / Jacques Quecq d’Henripret / distributed by AMF)
展覧会情報:
「シャセリオー展 19世紀フランス・ロマン主義の異才」
会期:2月28日〜5月28日
会場:国立西洋美術館
〒110-0007 東京都台東区上野公園7-7