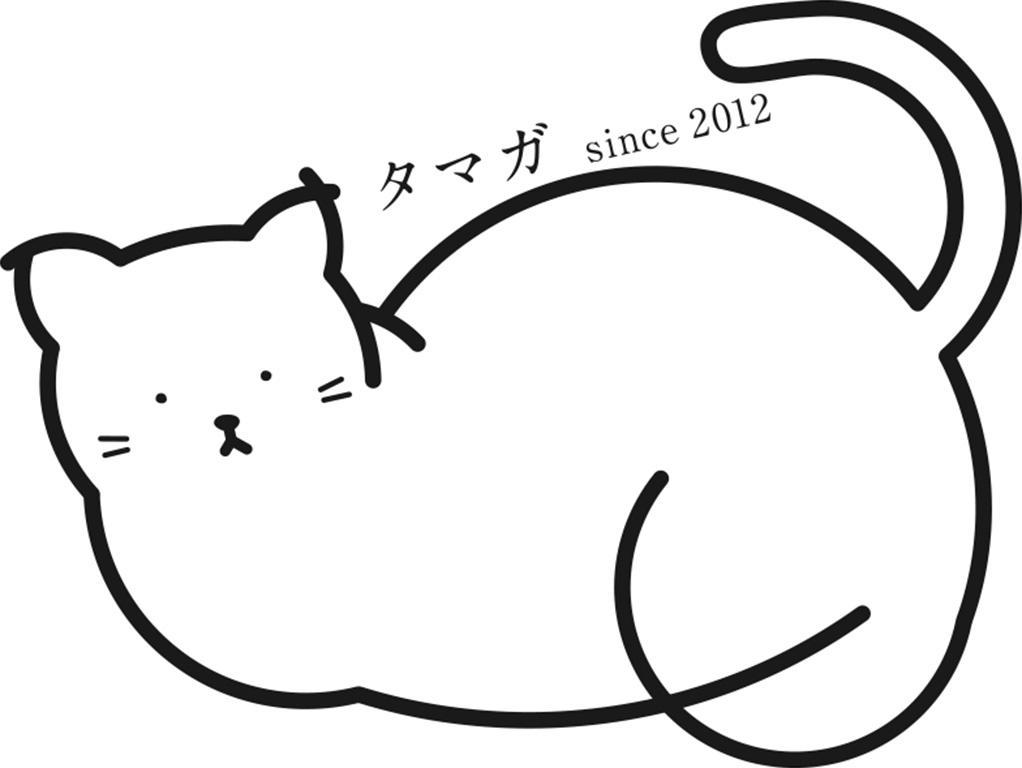大賞を受賞した京都絵美《ゆめうつつ》展示風景
館の移転などの事情から20年近くの間、開催されていなかった「山種美術館賞展」。その趣旨を継承した公募展「Seed 山種美術館 日本画アワード」が5月末に始まった。京都絵美(みやこ・えみ)の《ゆめうつつ》が大賞を受賞した。
意識の闇を描いたような世界に、眠ろうとしている女性が浮遊しているように見える。白と黒が基調の衣服はくっきり描かれているのに、手や足の表現はおぼろげで、闇の中に沈みかけている。「横たわる女性に夜空のイメージを重ねました」と、画家自身が書いたと思しき解説文にある。だが、女性がまどろみかけていることを考えれば、夜空を人間の深層意識になぞらえても、あながち的外れな想像とはいえないだろう。
この作品、技法と画題の親和性は高い。夜空あるいは意識の闇の、なんともいえない茫漠とした絵肌の表情は、東洋の画材ならではのもの。だからこそ、吸い込まれそうな深みが表現できているのではないか。
しかし、この作品が革新的かと問われれば、ためらわざるをえない。そもそも革新的な作品の出品は、全体的に少なかったようだ。審査員の一人、山下裕二明治学院大学教授はプレス説明会の席上で、「もっと型破りなものが出てくるといいなと思っていたが、わりとオーソドックスなものが集まった」と話している。
この賞は評論家などによる推薦方式ではなく、公募で出品作を集めている。今回の応募総数は259点。公募なら多様な作品が集まりそうなものだが、意外とそうでもなかったことになる。山下氏のように現代美術に明るい審査員もいるので、少々もったいないことのように思う。

審査員奨励賞を受賞した外山諒《Living Pillar》展示風景
そんな中で、プレス関係者の注目を大いに集めた作品があった。「審査員奨励賞」を受賞した外山諒(とやま・まこと)の《Living Pillar》だ。縦長の作品のほぼ全面に木目が描かれ、数匹の蛾(が)が留まっている。迫真性が高く、暗がりの中で光が当たっているような表現も効果的。本物に似せただまし絵のようですらある。
リアリズムや構図といった理論系の言葉でも、この作品の解説はできそうだ。ただ、なぜかそうすることに抵抗を感じる。美しい漆器、スマートフォンの裏面の金属板など、誰しも物の肌合いに無性に惹きつけられることがあるだろう。あるいは動物好きの人なら犬や猫の毛並みを想像してもいいかもしれない。この作品にはそれらに通じるような魅力があるのだ。視覚を通じて触覚に強く訴えかける。だから理屈を遠ざけるのではないだろうか。制作の動機について外山は、「法隆寺の柱に感動して描いた」と話す。素直に納得させられる言葉である。
ところで、外山が受賞した「審査員奨励賞」は、もともと予定にはなかったという。審査終了後、場所を変えての雑談の中ですべての審査員の口から気になる作品として名前が出てきて、予定していなかった賞をわざわざ設けたというのだ。なぜこの作品が最初から賞に選ばれなかったのか、といったところにも、明治以来の制度の上に成立した「日本画」というジャンルの今後の展開の鍵はありそうだ。賞においては丁寧で真摯な姿勢による審査が必須であることは言うまでもない。だが、ふっと力を抜いたときに見えてきたり表現できたりするものがあるのは、どんな仕事にもあることなのかもしれない。
取材・文・撮影=小川敦生

会場風景より。左から長谷川雅也《唯》、京都絵美《ゆめうつつ》、狩俣公介《勢焔》
【展覧会情報】
『開館50周年記念特別展 Seed 山種美術館 日本画アワード2016−未来をになう日本画新世代−』
2016年5月31日〜6月26日、山種美術館(東京・恵比寿)
大賞:京都絵美《ゆめうつつ》
優秀賞:長谷川雅也《唯》
特別賞(セイコー賞):狩俣公介《勢焔》
審査員奨励賞:外山諒《Living Pillar》
審査員 竹内浩一、佐藤道信、松村公嗣、宮廻正明、安村敏信、山下裕二、山﨑妙子
「タマガ」とは: 多摩美術大学芸術学科フィールドワーク設計ゼミが発行しているWebzine(ウェブマガジン)です。芸術関連のニュース、展覧会評、書評、美術館探訪記、美術家のインタビューなどアートにかかわる様々な記事を掲載します。猫のシンボルマーク「タマガネコ」は、本学グラフィックデザイン学科卒業生の椿美沙さんが制作したものです。